女鳥羽川沿いを歩く
ここは松本市の女鳥羽川。桜を眺めながら歩いている。
昨年、女鳥羽川の絵地図が出たということを記事に書いたので、せっかくなので桜の季節に川沿いに少し歩いてみようと思い立ったのだ。

人々が歩道で立ち止まって桜を撮影したり、川原でくつろいだりしている。海外からの観光客も多いようだ。
以前女鳥羽川の絵地図を見た時に、女鳥羽川と田川の合流地点のところに「犀川通船記念碑」があると書かれていたのを思い出し、今日はそこまで歩いてみることにした。
私も桜を撮影しながら歩く。

しばらく川原を歩いてみる。

川原から道路に戻って歩いていたら、JRの線路を過ぎた辺りで説明板を見つけた。

「③女鳥羽川の水の利用」という説明版だった。
これによると、昭和初期ごろまでは川沿いに製糸工場や染め物屋があり、製糸工場は水車を動力に使い、染め物屋は洗い水として水路の水を使っていたということが書かれていた。
川原を歩いていたので他の説明板を見ないでしまったが、他にも川沿いの道路にいくつか設置されているようだ。
このあたりは工事中のため川原は歩けない。
白板橋の架替工事のため、現在は旧橋のあった位置の東側に架けた仮設橋(写真の橋)が使われている。
工事は新たな橋の橋台を造る工事だそうだ。

仮設の白板橋を渡って少し歩くと、碑が建てられているのを見つけた。
石碑の土台部分に「犀川通船船着場跡」と記されている。

碑文を読むと、この碑は1968年に松本市が建てたものだった。
内容を要約すると、
1) 天保3年(1832年)に松本と信州新町を結ぶ通船として始まった。後に長野盆地まで伸ばした。
2) 明治になり通船は自由営業となって栄えた。明治初期に営業を開始した2軒の業者が1892年(明治25)に合併して新たに通船会社を設立した。
3)1902年(明治35)に鉄道の篠ノ井線が開通したため衰退した。
4)陸路犀川線(現在の国道19号)が開通し、1938年(昭和13)に通船は廃止された。
ということだった。
これは石碑に嵌め込まれたレリーフである。

明治20年(1887)頃の写真を元に作成したもので、赤丸(私が写真に書き込んだもの)のところにこの石碑を建てたと書いてある。
石碑の位置がここなら下流側から見た風景ということになるが、今よりも水面が高いように思える。昔は水が多かったのだろうか?
調べたら、1959年の台風での水害の後に女鳥羽川は拡幅工事を行なったとのことなので、それが関係しているのかもしれない。
石碑のところから見た、女鳥羽川と田川の合流地点。右下の水面は女鳥羽川だが、折れ曲がったその先は田川である。

私はここで引き返し上流側へ戻った。
中央大手橋の角に、旧開智学校跡の石碑が建っている。
以前はここに開智学校の校舎があったのだ。
1963年3月まで使われた校舎は、現在地に移築して博物館として公開されている。

この碑は2002年(平成14)に建てられたものだが、2019年に旧開智学校が国宝に指定されたことも記されていた。後で文字を彫り足したのだろう。

最後の写真は、千歳橋から見た上流側の風景。
夕方なので川原も少し薄暗くなってきた。


【関連記事】
「女鳥羽川の絵地図」(2024-01-29)





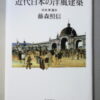

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません